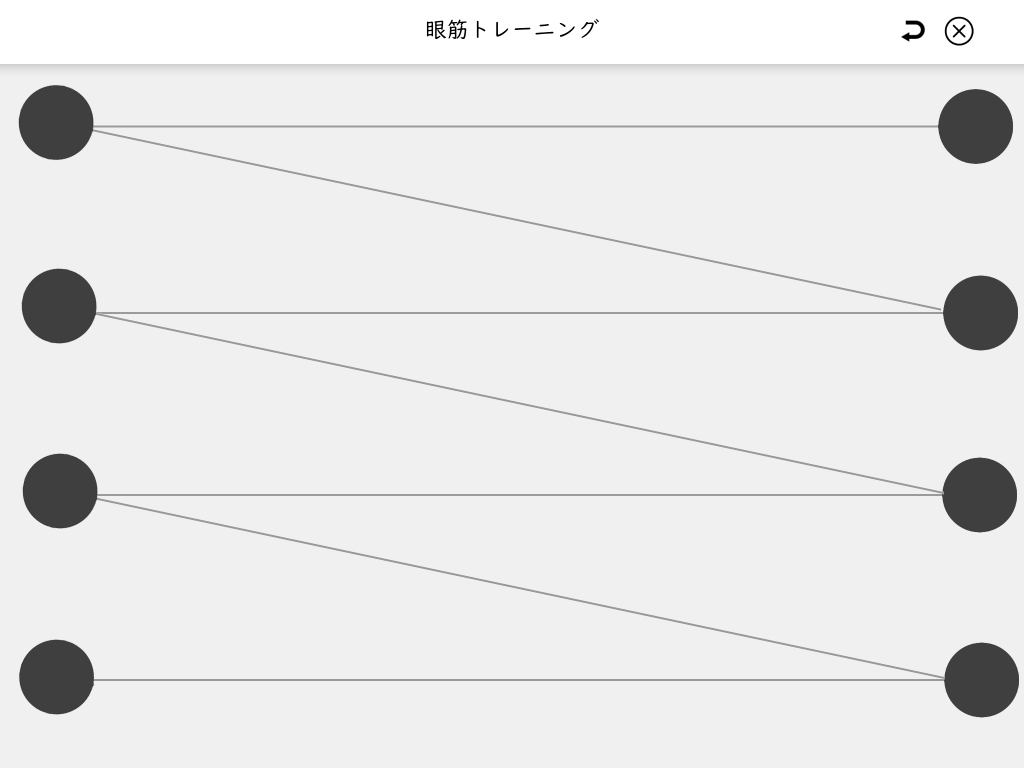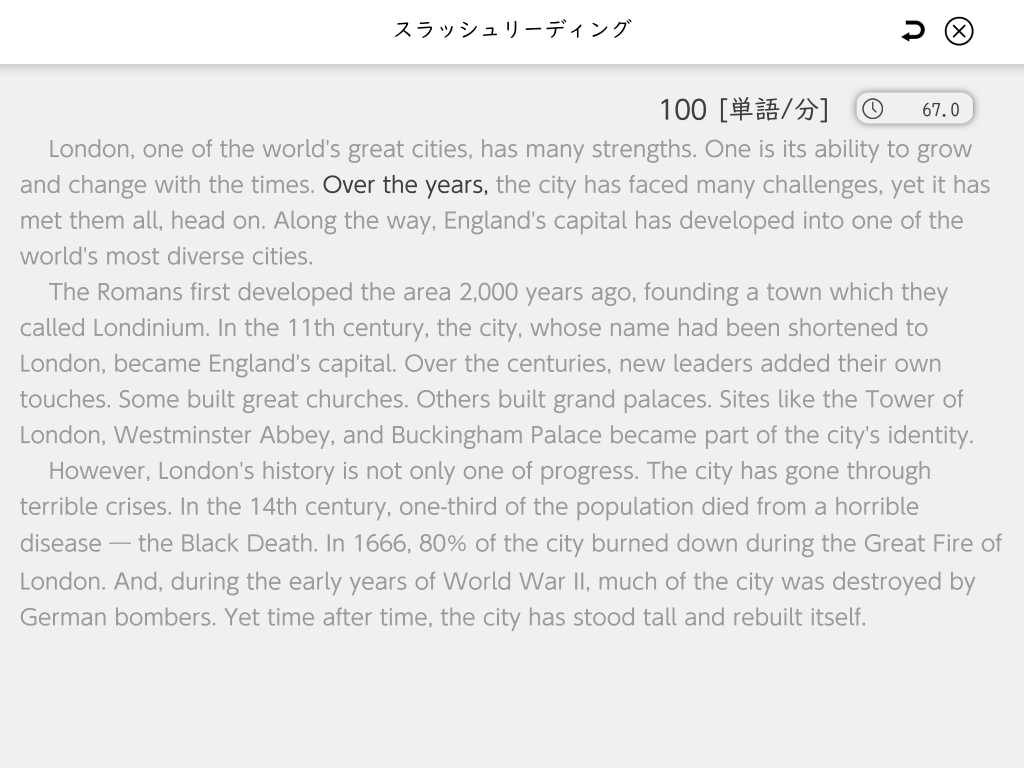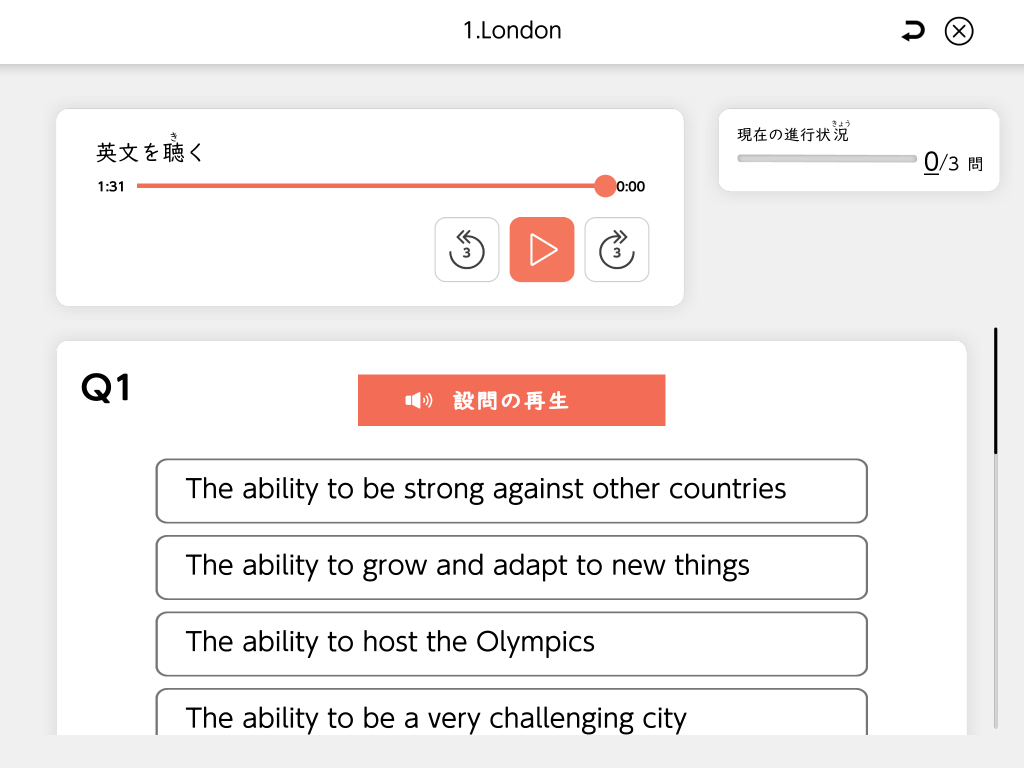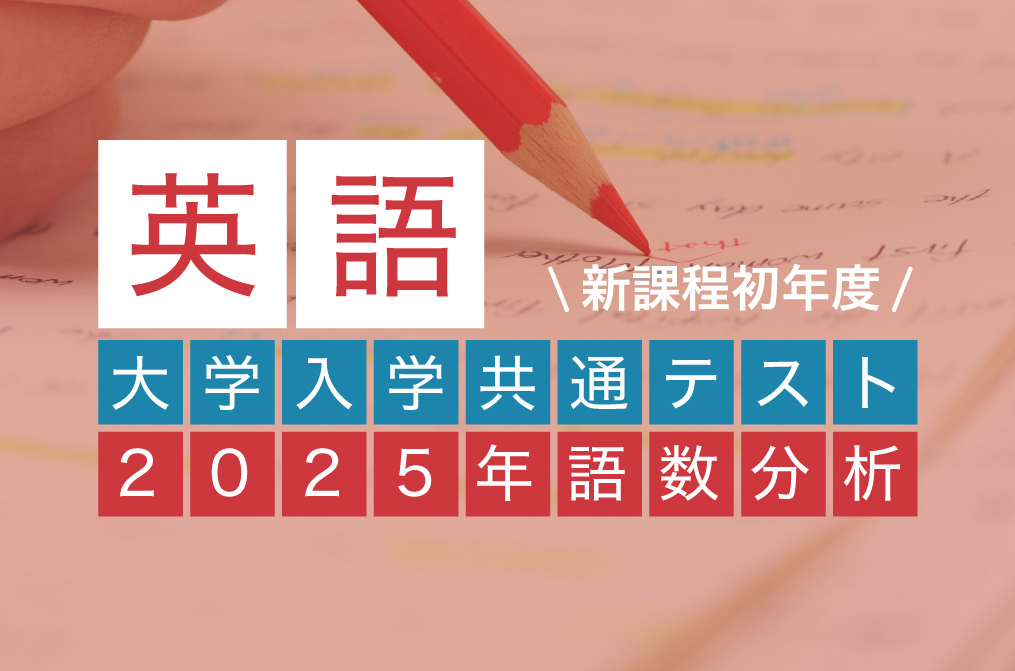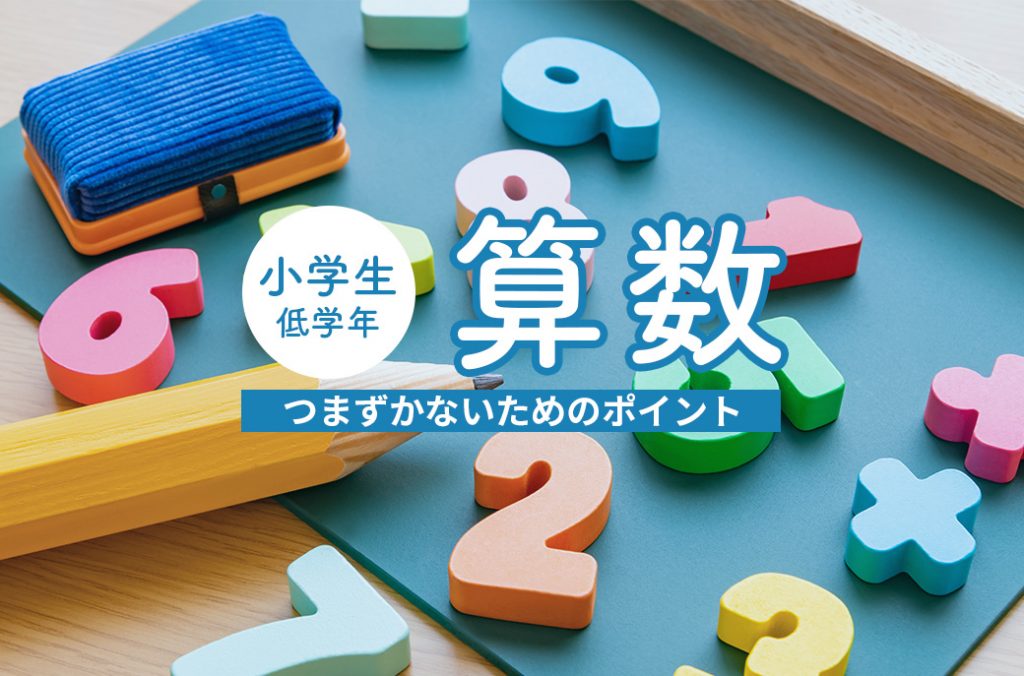元塾講師が教える!英語学習方法のヒント【英語が苦手な中学生へ・後編】
公開日:2025.03.19
この記事は4836文字です。
約4分で読めたら読書速度1200文字/分。
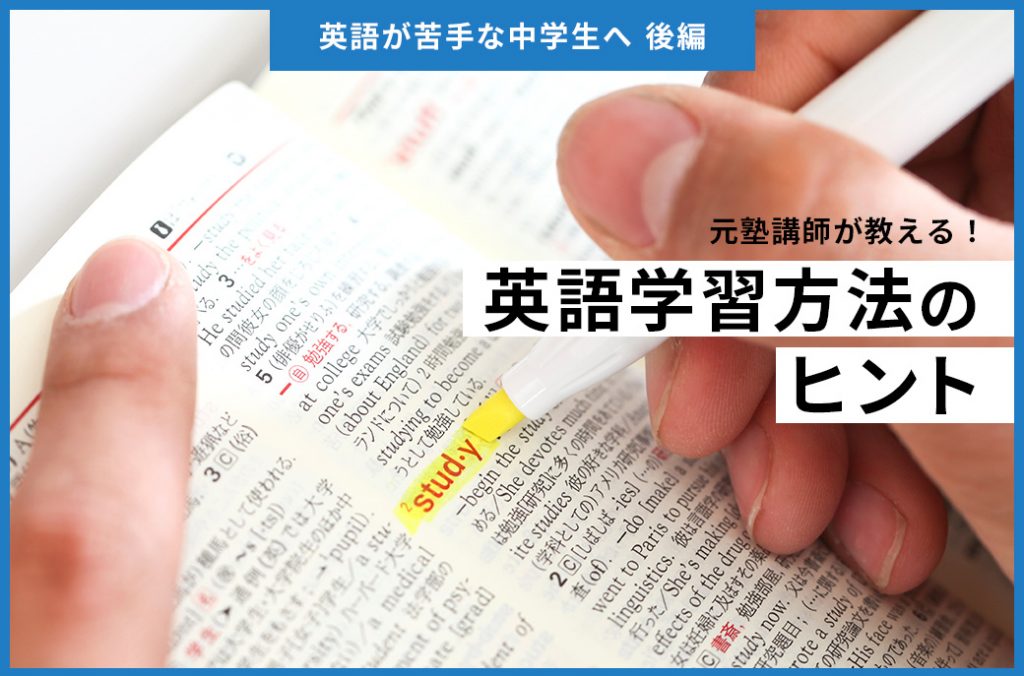
前編では「英語が苦手」と感じているケースの「苦手内容」にあわせて、その理由と解決のヒントをいくつか紹介しました。
後編は、前編とは違う視点で、英語の学習方法のヒントをお伝えしようと思います。
※この記事は後編となっています。前編はこちら。

ライター
安田 哲
一般社団法人 日本速読解力協会 理事
約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。
目次
勇気を持って戻る
英語が苦手な人は、先生から「いつから英語が苦手になったの?」と訊かれることがよくあると思います。
あの質問は、苦手になった時期から類推して「この辺りから復習しないとダメかな…」と見当をつけていますので、カッコつけて「(本当は中1の夏くらいからわからなかったけど…)中2ぐらいからです」と答えてしまうようなことのないようにしましょう。
また、自分で学年をさかのぼって復習した方がいいと感じることもあるでしょう。
そんな時に「自分は中3だから…中2ぐらいかな…」とするのではなく、少しでも不安要素が出てきたタイミングまで勇気を持って戻ることが重要です。
教科書の本文を読んでいって、スラスラと音読できなくなったり、読んでいて意味がわからなくなったりしたタイミングが「つまずきのポイント」です。
そのレベルからしっかりと学習内容を積み上げていくイメージで学習していくように心がけてください。
日本語と英語の違いを意識する
当たり前のことですが、日本語と英語は異なる言語ですから、いろいろと「違うなぁ」と感じるところがあるはずです。
もちろん、横書きにするときに左から右に書くとか、文の終わりにピリオド(日本語では句点)をつけるとか、似ている(同じ)部分もあります。
反対に、違うところもあり、その部分を無視していると「つまずき」から「苦手」になってしまいます。
ここでは、特に違う部分をいくつか紹介していきます。
読み方の違い
日本語は「高さ」で意味が変わりますね。
例えば「あめ」は「雨」なのか「飴」なのかで発音するときの高さが変わります。
「私の家では、父は『はし』でご飯を食べます」と言うときに、『はし』を「箸」と発音するのか「端」と発音するのかによって、お父さんの家庭内での位置づけが変わってきてしまいますね。
英語は「強さ」が意味の区別に関わり、必ず「強く読む部分」が単語に含まれます。
これを意識しないで平坦な発音をしていると、いつまでも英語らしい発音ができないばかりか、正しい意味で伝わらない可能性が出てしまいます。
いくつか例を挙げると、importは最初を強く読めば「輸入・輸入品」ですが、後半を強く読むと「輸入する」という意味になり、これは意味が大きく変わるわけではありません。
ただし、objectという単語は最初を強く読めば「物体」という意味ですが、後半を強く読むと「反対する」とか「異議を唱える」という意味になり、まったく違う意味になってしまいます。
誰(なに)が…?
日本語で「わかりましたか?-はい、わかりました」という会話を聞いて、「誰のことを言っているんだ!?」と疑問に思う人はいないはずです。
「(話し相手であるあなたは)わかりましたか?-はい、(聞いている私は)わかりました」の意味ですよね。
「だれが」というのを「主語」と言いますが、日本語はこれを省略しても文を成立させることができます。
※気づいている人もいると思いますが、じっくり考えると、上の例文で、「はい、わかりました」と「はい、私はわかりました」で伝わる意味が違いますね。
英語の場合は「わかりましたか?」を言うときには「あなたはわかりましたか?」と表現しなくてはいけません。
「ご飯はもう食べ終わったよ」は「私は」なのか「私たちは」なのかを明らかにしなくてはいけませんし、「来年アメリカに行くよ」も「自分がアメリカに行く」と伝えたいのか、聞いている相手に向かって「あなたは来年アメリカに行くよ」という海外転勤の話なのかわかりません。
「私は歩いて学校に行きます」を英語では、I go to school on foot. と言いますが、この I(私は)を省略して Go to school on foot. と言ってしまうと「歩いて学校へ行け」という意味になってしまいます。
こういった細かな違いに気を付けていけるようになるといいですね。
数の表現方法
英語を勉強していて「単数形」「複数形」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。
「1つ」を表す「単数形」と、「2つ以上」を表す「複数形」ですね。では、次の文で出てくる「手」と「ポケット」はそれぞれいくつあるでしょうか。
「ポケットに手を突っ込んだまま話してはいけません」
まず「手」は片手でしょうか、両手でしょうか。どちらの可能性もありそうですね。
次に「ポケット」は、おへそのあたりにある一つのポケットでしょうか、ズボンのポケットのように二つのポケットでしょうか。これもどちらの可能性もありそうです。
まとめると「片方の手を一つのポケットに」「両方の手を一つのポケットに」「両方の手を二つのポケットに」という可能性が考えられます(さすがに「片方の手を二つのポケットに」は難しいのでここでは考えないこととします)。
英語では、hand(単数形)と hands(複数形)のどちらになるのか、pocket(単数形)と pockets(複数形)のどちらになるのかを考えないといけません。
では「古池や 蛙飛びこむ 水の音」を英語にするときには、何の数を把握しなければいけないかわかりますか?
※答え…古池の数、蛙の数、水の音の回数
時間の表現方法
これは勉強を進めていくともっと複雑になるので、今の段階ですべてを書くことはできませんが、時間の表現の仕方も英語のほうがしっかりと使い分ける必要があります。
例えば「私の家は町外れに建っている」と「私の父はステージの上に立っている」の二つの文の「たっている」の部分の表現の仕方は異なります。
どちらも stand という単語を使うのは変わりませんが、ひとつ目の文は「今日も、明日も、一年後も変わらないこと」を表しているのに対し、ふたつ目の文は「少し目を離した隙にもう立っていないかもしれない」という可能性が含まれています。
わかりやすく言えば「ずっと変わらない」のか「すぐ変わる可能性がある」のかです。
このように、日本語では同じ表現を使うのに、英語では別の表現を使う場合があるので、英語で違う表現がされている場合にはその理由なども考えられるようになるといいですね。
文法は「学ぶだけ」ではなく「使うこと」が重要
一般的に「文法を学ぶ」というと、先生から文法を教わって(解説してもらって)、問題集やドリルなどで練習問題をたくさんこなす…というイメージが持たれると思います。
ただし、最近の研究では、このような学習をした場合の効果は長続きせず、半年や1年経つと効果は薄れていってしまうということがわかっています。
では、どうすればよいかというと、多くの英語の文章に触れていきながら、すでに教わった項目を身につけていくことが必要とされています。
文法を解説してもらって、文法用語を知っていたり、問題演習を重ねて100%理解できたように思っても、実際に使えるようになっていないと意味がありません。
文法を無視してよいというわけではありませんが「文法が完璧になってから先に進もう」という学習の仕方はあまりおススメできません。
日頃の英語の学習にあわせて、英文に多く触れていく機会を増やしていけるように心がけたいものですね。
もちろん、その時には音声もあわせてトレーニングしていくことを忘れずに!
豊かなインプットは豊かなアウトプットにつながる
英文に多く触れていく学習の方法をお伝えしましたが、このメリットは文法を定着させることだけではありません。
インプットしている量が多ければ多いほど、アウトプットするときの表現に工夫ができるようになります。
一つのことを言うのに、毎回同じ表現しかできないよりは、様々な表現方法を知っているほうがいいでしょう。
それだけでなく、いろいろな分野や題材について知識を持っていれば、相手とのコミュニケーションも弾むはずです。
インプットが「具材」、アウトプットを「料理」と考えるとわかりやすいかもしれません。
具材が少なければ、作れる料理も限られてきますが、具材が増えれば、料理のバリエーションも膨らんできますね。
逆に、「こんな料理が作りたい」と思っても、必要な具材が揃っていないようでは、その料理に辿り着くことはできません。
また、具材がたくさんあっても、料理に使わなければその具材はダメになってしまいます。
頭の中に「具材」を入れる(=たくさんインプットする)と、「料理」を作りたい(=実際に使ってみたい)という気持ちになるでしょう。
このように、インプットとアウトプットをバランスよく進めていくことが、英語の実力アップにつながるはずです。
速く正確に読む・聴く力を鍛える「速読聴英語講座」
「速読聴英語講座」は、自分の読むスピード(wpm)をもとにトレーニングが展開されますので取り組みやすい講座です。
目の動かし方に慣れる眼筋トレーニングや、英文を前から理解するためのスラッシュリーディングなど、読み方のテクニックを身につけることができます。
リーディングとリスニングの2技能に特化したトレーニングで、「音」と「つづり」と「意味」をセットで勉強できます。
初心者から大学受験生まで使える幅広いレベル別に英文を多数収録!英語をアウトプットする上で必要不可欠な「読む」「聴く」の技能を強化することができます。
- 速読聴英語講座【中学生向けトレーニング】 英文を速く正確に読む・聴くためのリーディングとリスニングの2技能に特化したトレーニングで、受験にも役立つ英語長文読解力を鍛えます。
- 体験教室を検索 速読聴英語講座を体験できる教室を全国から探すことができます。
まとめ
日本語と英語の違いを意識!
学ぶだけではなく使ってみましょう
- 不安を感じた時点まで戻って学習をする勇気を持つ
- インプットする英文が多いと、アウトプットの表現が広がる
学習していると日本語と英語の違いにつまずくこともあるかもしれません。小さな不安要素も苦手につながります。見て見ぬふりはしないようにしましょう。
また、やはりインプットは大事です。自分のレベルに合わせた英文に触れる機会を増やしていけると良いですね!